土曜講習楽しいぞ。
なかまくらです。
久しぶりに土曜講習で物理をやっています。
準備は大変。4時間くらいかかっている気がします。
受験科目になる可能性は低いけど、推薦で大学入ったら使うから・・・
なんて言って取ってくれている希望者とやっているので、みんな意欲が高い!
物理で遊ぼう!なんだと思います。
問題を解いて、こんな設定か~! これ、どうやって解くんだよ~!!
と、1時間、ああでもないこうでもないとみんなで考えて解いていくことを楽しむ。
楽しい時間ですね。
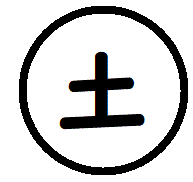
久しぶりに土曜講習で物理をやっています。
準備は大変。4時間くらいかかっている気がします。
受験科目になる可能性は低いけど、推薦で大学入ったら使うから・・・
なんて言って取ってくれている希望者とやっているので、みんな意欲が高い!
物理で遊ぼう!なんだと思います。
問題を解いて、こんな設定か~! これ、どうやって解くんだよ~!!
と、1時間、ああでもないこうでもないとみんなで考えて解いていくことを楽しむ。
楽しい時間ですね。
