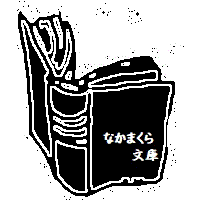【小説】未明
なかまくらです。
物事を学ぶということについて。
小説です。どうぞ。
「未明」
作・なかまくら
物事を学ぶということについて。
小説です。どうぞ。
「未明」
作・なかまくら
「おとぉうさん、火が出ないよ」 まだエンキが小さかった頃の記憶だ。時々夢に見る、断片的な情報の羅列。エンキは左側頭部で主張の激しいアホ毛がトレードマークで、まだお父さんとちゃんと発音できなかった。同年代の子供に比べて少し発音が苦手だったかもしれないが、特に問題はなかった。夢の中を見渡せるようになったのは、同じ夢を10回見た頃のことだ。キッチンのカレンダーは10月。何歳かは覚えていない。お母さんはその時、家にはいなくて、お父さんがキッチンにやってくる。ズボンはいつも絵の具がついている。お父さんは絵を描くのが好きで、朝、空が明るくなってから、暗くなるまで絵をかいて過ごしていた。「サンセットがいいんだ。赤なのに、赤だなあとは思わない。何か大切なことを忘れているような寂しさや怖れとか、理由もわからない感情が湧き出してくるんだよ、だから好きだ」お父さんはよくそう言っていた。
「火が出ないって?」 お父さんは、つまみをしきりに捻って、続いて首をひねった。
「おかしいな」 そう言って、火にかけようとしていた鍋のスープをコップに移してレンジでチンした。「少し出かけてくるから、しばらくはこれで対応しなさい、分かったね?」「はぁい」
何も解決してないじゃないか、とは言わなかった。暖かいスープがエンキの手の中にあった。結果としては一緒だった。
しばらく、とはどれくらいの期間を指すのだろうか。カレンダーは自動的に表示内容を11月に変え、12月に変えた。それから、また12月が来て、そして12月になった。それを8回ほど繰り返して、エンキは15歳になっていた。その間に弟が生まれた。母があなたの弟よ、と連れてきた。父は調べたいことがあるからしばらく留守にする、と言って帰ってきていない。
「しばらく・・・」
朝ご飯は、家の中央の柱のドアを開ければ用意されている。それを家族の分だけ食卓へ並べるのはエンキがいつもやっていた。
「お母さん、サン、ご飯だよ」 母と弟を呼ぶ。
「1,1,2,3,5,8,13,・・・」 弟のサンは時折、わけのわからないことを考えている。
「なんだそりゃ?」
「13の次は?」
「分からないけど・・・」
「2つ前の数と1つ前の数を足すと、その数になるんだよ」
「でたよ、足し算、だっけ?」
「そう、算数とボクは呼ぶことにした。だから8たす13は21だ」
「たすというのは、合わせる、ということだろ? 1,2,3・・・20、21だ」 エンキは手の指と足の指を総動員して、最後に1だけ足りない分は首を前に倒して数えて用を足した。
「確かにそうだよ。けどさ、サン。それが一体、何の役に立つんだい?」
「分かんないかなぁ・・・」 サンは勿体ぶってそう言って、「まあ、ボクにも分からないんだけど」そう言って、頭を掻いた。「たださ、役に立てる方法を知らないだけなんだよ」サンは何か遠くのほうを見ているような気がして、エンキはとりあえず、頷いた。
そして、水が出なくなった。
気づいたのは、母だった。サンが、キッチンの水の口のつまみをひねる。サンは首をひねらなかった。
「兄さん」
「なに?」
「なにか硬い、尖ったものがないかな? キッチンの下をこじ開けるよ」
キッチンの戸棚はずいぶんと硬い物質でできていた。庭の木の枝を切って打ち付けた。すぐに折れた。道路に敷き詰められている石畳の欠片を叩きつけてもほとんど変わらなかった。移動式のキャビンを思いっきり投げつけると少しだけ歪む。その隙間に枝を差し込んで、打ち込んで広げていく。蓋の中は、よくわからない点滅を繰り返す色とりどりの光が溢れていた。その中で二つが色を失っていた。その管の伸びている先は、火の口と水の口につながっていた。
「どういうこと?」
「どうもこうもないよ。ボクらは、そう思うことを許されていなかったんだ・・・」
「ごめん、何を言っているか分からない」 エンキは、不安の声を上げた。いや、分かっている。感覚としては分かっているが、それをどう言い表してよいのかわからないのだ。
「ずっと思っていたんだ。これを誰が作ったんだと思う?」
「分からない」 エンキは首を振った。
「これは?」 サンは、食べ終わった朝食のトレイを指さした。
「分からない」
「お母さんは?」
「知らないね。そういうものだと思ってたから・・・」
「そうなんだよ。つまみをひねれば火が出たり、水が出たりする。それは、そうだけれど、そうじゃない。‘火‘とはなんだろう、‘水‘とはなんだろう、ということなんだよ。そしてボクたちは何だろう、ということなんだよ。」
エンキは、ふいに自分たちがひどく小さな場所に閉じ込められているような気がしていた。自分たちの足元がひどく不安定で、それをどうにかする方法が見当もつかないことに気づいた。
「どうしたらいいんだ?」 エンキはサンに答えを求める。
「分からない」
その答えにエンキは落胆する。
「兄さん、落胆するんじゃないよ、こういうときは。ボクたちは問題を見つけた。あとは解くだけなんだ」 サンの声は、決して絶望ではない、と思わせてくれた。むしろ、ワクワクするような、先がどこまでも広がっていくような・・・。
「お前は、何者なんだ・・・?」
「分からない。母さん、ボクはどこからきたんだい?」
「16になるときに話すしきたりなのだけど・・・いいわ。子どもは、まれに朝食と一緒に届けられるのよ・・・」
「そうしたら、俺たちは、こうやって食べているものと何が違うのだろう? 間違えて食べないのはなぜだろう? 食べているものはなんだろう?」 エンキの中からは疑問があふれ出していた。
「ボクは時折、見たことも聞いたこともないことが浮かんでくることがあるんだ。それはボクがどこかから来たから、なんだね。探しに行こう、そのどこかを・・・」
それから、街の中央広場の噴水広場に人々は集まった。噴水の水は絶え、その理由を誰も知らなかった。噴水の像に縄をかけ、引き倒すと、大きな縦穴が現れる。その穴に調査隊を送る。その先頭にはサンとエンキもいた。
サンが言う。次に起こることは何だと思う?
エンキは想像もつかない、という。
サンは、笑う。たぶんね、呼吸ができなくなる。吸っているもの・・・これをサン素と名付けようと思う。これを作る方法を探さないといけない。サンは、いたって真剣な表情だった。
地上では、天の欠片が一つ、広場に落ちたところだった。