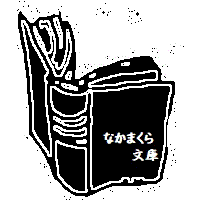【小説】アホ毛を切って
なかまくらです。
久しぶりに小説です。
なんとなく後味が苦めなのは気のせいじゃないです。
着地しようとしたら、なんか自分の中の何かが邪魔してきた感じで、
こうなりました。
どうぞ。
ーーーーーーーーー
「アホ毛を切って」
作・なかまくら
久しぶりに小説です。
なんとなく後味が苦めなのは気のせいじゃないです。
着地しようとしたら、なんか自分の中の何かが邪魔してきた感じで、
こうなりました。
どうぞ。
ーーーーーーーーー
「アホ毛を切って」
作・なかまくら
「ね。お金なんだけどさ・・・」
そう切り出す友人に、内心嫌悪感を覚えながらも顔には出さないように気を使った。
「ああ、いいよ。せっかくまた会えたんだから」
カードをかざすと、私の情報が照合され、働いている場所、支払いに滞りのない信用できる人物であるか否かを照会される。そして、特に問題のない人物と判定され、「ピ。」と支払い完了の効果音が鳴る。
「ごめんね」
「そういうの、やめてって」
「うん」
「・・・」
高校生の時はそういう関係ではなかった。勉強ができるとか、できないとかではなくて、気が合うとか、そういうことしか考えてなかった。私は勉強はできたけれど、勉強のできることを良いことに、いかにもそれらしく振舞う連中になりたくはなかった。友人は、そんな私の気の置けない友人だった。音楽が好きだった。好きなバンドを追いかけるためにアルバイトで軍資金を稼ぎ、全国を巡る高校生だった。夢中で話す友人の話に、たいした夢のない私は耳を傾けて、少しだけそれを分けてもらっていたような気がしていた。
私が大学へ行って、友人が就職して、まもなくある装置が発明され、それを使ったサービスが始まった。「働き足りないあなたへ・・・」というコピーで、駅のホームに大きな看板が何枚も並んだ。AFO(Anti Fiction Object)という名前のその装置は、睡眠を売買できる装置だった。売ってしまえば、売った側はその夢を見たことは忘れる。買った側はその夢を見ると同時に、思考が整理され、頭がすっきりするという触れ込みだった。その頃の私は、大学の講義についていくのがやっとで、けれども学費も稼ぐためにアルバイトもしなければならない状態で、ひどく疲弊していた。それで、興味本位で調べてみると、サービスの提供価格は当時の私にはとても手の出ないものだった。
「ね。聞いてる?」
「あ、うん・・・何の話だっけ?」
「疲れてるんでしょ、一流企業に勤めるサラリーマンは辛いですなぁ」
「いや、そんなことは・・・あんまりないよ」
「ちょっとはあるんだ」
「まあ、多少はね。そっちはどうなの?」
「からっきし。だから副業とかもしててさ」
「副業?」
「今、流行ってるんだよ、個人投資家ってやつ。あとはWEBで記事書いてさ、広告収入?」
「投資? 危なくないの?」
「古い! ・・・古いよぉ。大丈夫だって、みんなやってるし」
「それにしては・・・そんなに羽振りがいいようには見えないんですが?」
「てへへ、ちょっと今月はピンチなのです。・・・あ、そろそろ行かなくちゃ。このあと仕事でさ。じゃあね、また」
「・・・うん」
何かが喉の奥のほうで詰まって・・・またね、という言葉は飲み込んだままになった。それが何か、感覚的には分かっているような気がしていた。
*
翌日からは仕事に戻った。朝早く出社してデスクに山積みにされた仕事を黙々と片付けていく。時計と書類を交互にチラチラとみる時間がしばらく続いて、それから同期と連れ立ってランチに出かける。
「ねえ、AFOって結構いいらしいよ」
「へぇ・・・なんか危なくない?」 私も聞いたことがあった。
「心療内科が治療に使ってるくらいになっているみたい。保険適用はさすがに難しいかなぁ・・・」
「睡眠障害の人とか、立ちどころに治っちゃう! みたいな?」
「へぇ~・・・」
あくびを噛み殺しながら、私は大学生のころに見た料金を思い出していた。
「一度行ってみてもいいんじゃない? ほら、最近いつも眠そうだし」
「うん、そうかもね」
「あー・・・、ただ、装置を使うとアホ毛がとまらないんだって。副作用で」
「アホ毛、って、あのアホ毛?」
*
店へと向かう道すがら、それだけが気になっていた。あの、久しぶりに会った友人の、アホ毛だらけの髪の毛が脳裏から消えなかった。
店は、整体院のような佇まいであった。90分のコース、180分のコース、270分のコースがあり、それぞれに値段が設定されていた。サービスの普及とともに安くなってもいいものだが、まだそんなには安くなかった。ちょっと豪勢な宿に一泊するくらいの値段であったが、財布を取り出して支払った。
夢の中では、好きなバンドがあって、そのために一生懸命お金を貯める女の子だった。そのために、お金を稼ぎ、それに見合う格好をするためにお金を稼いで、友達に自慢した。それが何よりも楽しかった、輝いていた・・・・・・夢の外の本当の私は、学生だった頃、そんなことを思ったことはなかったけれど・・・。
誰が売った夢なのか、直感的にわかってしまった。
効果は抜群で、ここ最近、ずっと心の中でジトジトと湿り気を帯びていたものがどこかへ行ってしまったようだった。
けれども、明日、友人を呼び出そうと思った。自分は、ついにお金も仕事も夢もすべてを手にしてしまったけれど、では、あなたから何を奪ってしまったのだろう。もう友人ではいられないのかもしれない。夢を語り合えなくなってしまったのかもしれない。
だから、「私にとってあなたは、夢を語る人であり続けてほしい」と伝えよう、と思った。
そうしたら、アホ毛を切って、カフェに行って、履歴書を一緒に書くのもきっと素敵だ。そして、いつか分かってもらえる日が来たら、私たちはまた友人になれるだろう。