【小説】アイディアの王国
なかまくらです。
久しぶりに小説です。この作品ですが、やっと書き上げた小説の一つです。このタイトルですが、本当に何度も挑戦したタイトルでした。最初に書いたのは、23才、大学院1年生の時でしたが、書き上げたものの、どこか納得がいかなかったのでした。それから、10年、時折思い出しては書いてみたのですが、書き上がらなかったのです。
それをようやく書き上げました。ちょっとは実力がついていると言うことなんでしょうか。
ともかく、どうぞ。
*******************
「アイディアの王国」
作・なかまくら
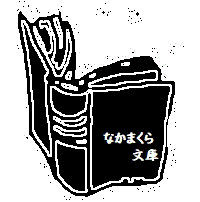
久しぶりに小説です。この作品ですが、やっと書き上げた小説の一つです。このタイトルですが、本当に何度も挑戦したタイトルでした。最初に書いたのは、23才、大学院1年生の時でしたが、書き上げたものの、どこか納得がいかなかったのでした。それから、10年、時折思い出しては書いてみたのですが、書き上がらなかったのです。
それをようやく書き上げました。ちょっとは実力がついていると言うことなんでしょうか。
ともかく、どうぞ。
*******************
「アイディアの王国」
作・なかまくら
1.
どこか古い洋館のようなそこに行けば、物語に出会えると聞いた。
工場の煙に包まれた町の外れまで行って、その先に広がる見渡す限りの耕作地帯も通り抜けて、それでもなお自転車を飛ばしていくと、その建物はあった。
両開きのドアを片方だけ少し開けて中に入ると、本が多く置いてある場所特有のインクのにおいがした。エントランスの中央に置かれた受付のカウンターまで歩いてみる。
「こんにちは」
声が2階、3階へと響くが、返事はない。扉を数えると、見える範囲では8つの部屋が見えた。
「あ、」
振り返ると、入り口から入ってきた青年が見えた。髪は縮れて長く、目を覆い隠していてその表情は知れない。脇には紙の束を持っていた。
「あっ、すみません」
「・・・っ」
縮れ毛の青年は、顔をそらして逃げるように階段へと向かっていく。
「あ、あの・・・」
青年はそのまま3階までいそいそと上がると、扉を開けて、静かに閉じた。ひらりと一枚の紙が落ちてくる。拾った紙には、「世界のたわし」と書いてあり、そこには多くの図版が載っている。
「たわし・・・?」
そこに、一節だけ、走り書きのように書かれている言葉が目に入る。
“わたしの代わりにたわしを置いていくの“
その瞬間に、何かが頭の中を駆け巡って、膝から崩れ落ちる。それは一体、どんな物語だろうか。身代わりにたわしを置いて、自由になった誰かの顔はほとんど見えないけれど、ニッ、と笑ってどこか遠くのほうに飛ぶように行ってしまった。
「あああ・・・」
大変なことをしてしまった、という罪悪感が、通り過ぎていった物語の強い刺激に飲み込まれていく。跡形もなくぐしゃぐしゃに潰されて、ほぐされた小さな心がぽつんと残って呻いた。
「・・・ああ」
2.
「物語の始まりのようだよ!」
受付の奥の扉が開き、声のしたほうから初老の男が歩いてくる。
「大変申し訳ございませんでした!」
謝るしかなかった。
「落ちてくる紙、拾うあなた。こういうときには預かりましょう、彼に届けますよ?」
「できれば自分で届けて謝りたいと思います」
「いいでしょう、そうこなくっちゃ。そうやって物語の登場人物に人はなっていくのです。彼のことを少しだけお話ししましょうか?」
「え、ええ・・・でもその前に・・・」
「その前に・・・?」
「あなたのことを少し教えてもらってもいいですか?」
「おっと、そうですか。私は、短編小説の道先案内人。たいした者ではないんですが・・・」
男は帽子にふわりと手を乗せると、大きく円を描いて膝まで持ってくる大仰な礼をする。
「・・・ここの管理人をさせていただいております、Uと申します」
「ご丁寧にありがとうございます・・・私は佐倉と申します」
「どうも、佐倉さん。ああ、その紙については、お気になさらずに。その物語は世に出ませんよ、たいした物語ではなかった」
「いえ、そんな・・・申し訳なかったです。こんなにも、こんなにも愛おしいものだとは」
心からの悔恨の想いをよそに、Uはどこか愉快な道化のようにどこかに誘おうとする。
「・・・して、今日はどうしてご来館を?」
ドキリとした。新しい物語は貴重で、リリースを待たなければならないものだからだ。
「あの・・・すみません、道に迷ってしまったんです」
変哲のない嘘しか出てこなかったが、Uは笑わなかった。
「あなたも薬は飲んだのでしょう?」
「・・・はい」
「食料もエネルギーも限られてしまった現代において、民衆はそれを受け入れるしかありませんでしたから」
「・・・私はまだ物心がつく前だったんです」
「意識の研究が進んだ現代において、そのサイエンスフィクションのような解決手段が考えられました。全体の意識を深層において中枢につなぐことによって、人々を一つの目標に向かわせようとする力学が生じるようになりました」
それにより、今までは成しえなかった我慢を理解できるようになったという。
「でも、その代償は大きかったと聞いています。そして、先ほどそれを知りました・・・」
佐倉はあの物語体験を一生忘れることはないだろう。
Uは怒りの籠っていない声で言う。
「分かっていたのですよ、政府の人々は。彼らはその生き残りを掛けて、物語を捨てることを決めた。一度誰かに読まれた物語は、誰にとっても一度読まれた物語となってしまうようになりました」
「物語というものに出会うということは、自分ではない誰かに出会い、自分を見つける体験なのですね」
「さあどうでしょう」
Uは、そう言って笑った。
それは、その人がどんな風に生きてきたかにもよるのさ。
3.
その洋館には一部屋の空きがあった。
佐倉は庭の掃除をしながら、そのカーテンの閉まったままの部屋を見上げていた。佐倉は期間使用人となった。洋館の庭に建てられた小屋には、彼の少ない私物を置いてある。開いてしまったアイディアの対価ということだ。
落ち葉を掃き終わると、洋館のほうから、悲痛な声を上げて、寸胴で鼻の大きな中年の男が駆け寄ってくるのが見えた。ニシヅカさんだ。
「きみ! きみは、いったい、何だね!?」
「あ、こちらでしばらくお世話になります、佐倉と申します」
ぺこりと、頭を下げると、そのまま頭を叩かれた。
「名前なんて、なんでもいいんだ! 問題は、きみが、この、芸術的な、落ち葉を掃いてしまったことにあるのだということに、なぜ気づけないのだ!」
中年の男は、きっとこの落ち葉に物語を見たのだろう・・・。佐倉の中には具体的な像は結ばれず、被害は起こらなかった。しかし、そこから生まれるはずだった物語は、誰かにとってかけがえのない物語だったかもしれない。佐倉は、申し訳ありません、と謝る。
「以後、気を付けるように・・・」
中年の男も、それ以上は何も言わず、集められた落ち葉をしきりに見ていた。
そこに、落ち葉を散らせて、Uの車が戻ってくる。
今日は工場区画を抜けたその先、中枢区へ献本をしに行っているはずだった。そこから戻ってきたのだろう。そう思って、見ていると、後部座席から、一人の少女が降り立った。年齢は13~15才くらいだろうか。
「どうしたんですか?」
「彼女に部屋を案内してやってください」
彼女はどこから、なんのために、ここにやってきたのだろうか。3階の階段から一番遠い東側の部屋が彼女にあてがわれた部屋になる。佐倉は、階段を上りながら、ちらりちらりと横目に彼女を見る。その着ている服から大事に育てられていたように見える。
「こちらへどうぞ」
「・・・・・・あ、」
扉の枠を飾る龍の彫刻に目を奪われた彼女は、声を掛けてもうんともすんとも言わなくなった。佐倉はしばらくそれを待つことにする。ここには変わった人が多い。普段、気にかけないような小さな石に躓き続けている人たちが集まっている。でも、その石が新しい物語の原石なのだと思えてくる。だから佐倉はそれをそのままにしておくことにしていた。
4.
「こんばんは。少しいいかな」
管理人のUが、小屋にいた佐倉に声を掛けてくる。
「珍しいですね、こんなところまで。紅茶でいいですか」
「ああ、頼むよ」
コートを預かり、壁に掛ける。それから、薄暗い部屋にランプに火を入れる。夜はずいぶんと冷える季節になっていた。
「彼女、少し違うでしょう」
座ったUが、そう言った。
「そうですか」
佐倉は、Uの意図が図りきれず、相槌を返す。
「彼女はね、アーティストの才能があると見込んでいるのです」
「アーティストですか?」
「そう、アーティストはね、味を加える人なのですよ」
「味を加える人」
「新しい価値観や要素を社会に加えることができる人種です。それがどういうことかわかりますか」
「さっぱりです」
「これは難しい話になります。主義主張もあるでしょう。しかし、私はあなたが鍵になると踏んでいます。あなたは深層ですべての人と繋がっている。そして、あなたは物語に対する感受性が高い。だから、あなたを通して、すべての人にアーティストである彼女の物語を届けることができると思うのです」
静まり返った寒い夜だった。Uの顔は怪しく微笑んでいて、それをランプの灯が揺らめいて、表情を確定させない。佐倉はそれに恐ろしさを感じた。ただ、同時に・・・、
物語の始まりに出会える興奮を抑えることができずにいた。
