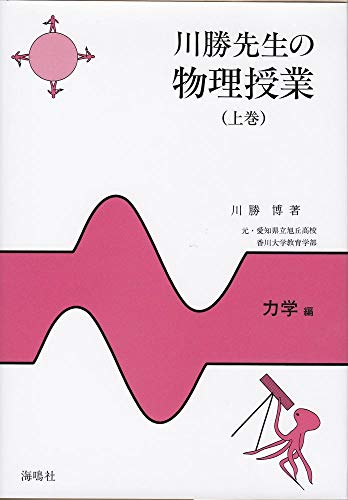なかまくらです。
「大雪海のカイナ ほしのけんじゃ」観ました。

弐瓶勉さんの作品で、アニメシリーズに続いての劇場版です。
「シドニアの騎士」に続いての、ポリゴンピクチュアと弐瓶勉のタッグです。
あらすじ。
雪海(ゆきうみ)におおわれた星は、地表がはるか下の方に埋もれてしまっている。
雪海は、海のようであって、海ではない。
浮袋がないと、浮かんでいられないし、海のようであるけれど、水ではないから、
飲むことはできない。生き残った人々は、軌道樹と呼ばれる樹が地表から吸い上げる水
を頼りに生活していた。
しかし、軌道樹が枯れたり、水を奪い合う争いによって、人はその数を減らし続けていた。
カイナは、そんなことも知らずに、軌道樹の上に広がる天膜の上で、
老人たちと暮らしていた。
そこに、アトランドの王女リリハが賢者を探しにやってきて、物語は動き出す。
カイナとリリハは、軌道樹を持たずに、他国を侵略して回っているバルギアから、
アトランドを守るために奔走する。そして、TVシリーズの終わりに、それは
成し遂げられる。その過程で、大軌道樹への航路が示された地図を見つける。
老人たちからの教えにより失われた文字を読む能力を持つカイナは、
それを目指すという希望を与える。
船が大軌道樹に辿り着いた国は、プラナトという場所だった。
高度に発展した過去の人類の文明を色濃く残す場所は、
ビョウザンによる支配がなされていた。
ビョウザンは、軌道樹を切り倒すことによって、雪海を取り払う計画を立てていた。
そのためには、精霊(?)に認められた人間だけが手にすることのできる
指揮権者の服が必要だった。それを手にすることができると思われた
カイナとリリハは、協力を求められるが、これを断る。
そのやり方では、多くの人死にがでることが明らかであった。
強制的に連行され、働かされるアトランドの仲間たち。
カイナは、その果てに、この星の真実を知る。
大軌道樹は、星をテラフォーミングするための一時的なものだったのだ。
そして、その時はすでに過ぎていることも。
真実を知ったカイナは、リリハとともに、ビョウザンの悪行を止め、正しい方法で、
星を始めるために、動き出す。
みたいな話でした。
この作品、どこかのんびりだけれども、とても厳しい世界観で、好みです。
ちょっとご都合主義も強いかなという側面もありますが、
冒険譚としてわくわくしながら楽しく見られるSF映画でした。
途中のいろいろがナウシカっぽかったり、
ラストは、急にラピュタになったり思わず劇場で笑いそうになりましたが、
まあ、過程は全然違うので、オマージュということでしょう(笑)。
評価したいのは、こういうお話にありがちな、おれたたエンドではなくて、
結末がちゃんと用意されていたことです。これからの希望ある終わりに◎
そして、歌がいいんです。すごく世界観にあっていました。