夜ノヤッターマン3話 俺たちは天使じゃないけど天使のフリをする
なかまくらです。
夜ノヤッターマン3話も課金して観ました。216円/話でニコニコ動画で見られます。
2話の最後に登場した盲目の女の子はアルエット。

彼女は、ドロンジョを願いをかなえに来てくれた天使だと勘違いをする。
そこに現れるアルエットの幼馴染、ガリナ。

ガリナから、ヤッターマン一味に連れ去られ、強制労働の果てに死んでしまった
2人の両親の話を聞く。アルエットはまだ、その現実が受け止められず、
逃避しているのだという。
そこに現れるヤッターマンロボ。
ガリナは、さいころを振り、ドロンボー一味を助けることを決めた。
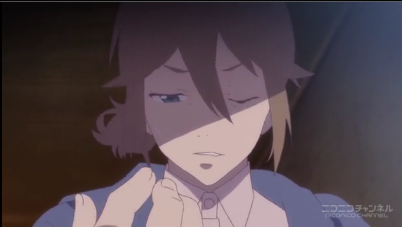
押し入れの中のドロンジョ(レパード)かわいい。

ヤッターマンロボ。こわい。

なんとかやり過ごしたドロンボー一味は、朝早く、家を出ることをガリナに約束した。
ガリナに何故、戦うのかと聞かれたボヤッキー、トンズラーは、
「大切な人を守れなかったから」
そう言った。
ガリナは、夜なべをして、ドロンボー一味の衣装を縫い、それを託す。

ドロンボー一味が去った後、アルエットの家を、ヤッターマンロボが襲撃していた。
2人の居場所を言え!
そこに戻ってくるドロンボー一味。
「お前たちを守る!」
一緒に進むことを自分で決めるガリナ。
燃え盛る家から現れる正装のドロンボー一味。かっこいい。

「お前たちは本当の正義なんかじゃあない!」
「清く正しく美しく! ドロンボーがいるかぎり、この世にヤッターマンは栄えない!」
「闇をはらい、この世界に新たなる夜明けを!」
ボヤッキーのロボで窮地を脱出するドロンボー達。
(続く)。
まさかのみんなで行く展開に。特にすごい力があるわけでもないけれども、
仲間が増えて、進んでいくのですね。
衣装で登場するところはかっこいいですねぇ。
「お前たちは正義なんかじゃあない!」というところ、いいですねぇ。
まさにその通り! ヤッターマンは悪党だ! 気持ちがスカッとしました。
この後、どうなっていくのでしょうか。
夜ノヤッターマン3話も課金して観ました。216円/話でニコニコ動画で見られます。
2話の最後に登場した盲目の女の子はアルエット。
彼女は、ドロンジョを願いをかなえに来てくれた天使だと勘違いをする。
そこに現れるアルエットの幼馴染、ガリナ。
ガリナから、ヤッターマン一味に連れ去られ、強制労働の果てに死んでしまった
2人の両親の話を聞く。アルエットはまだ、その現実が受け止められず、
逃避しているのだという。
そこに現れるヤッターマンロボ。
ガリナは、さいころを振り、ドロンボー一味を助けることを決めた。
押し入れの中のドロンジョ(レパード)かわいい。
ヤッターマンロボ。こわい。
なんとかやり過ごしたドロンボー一味は、朝早く、家を出ることをガリナに約束した。
ガリナに何故、戦うのかと聞かれたボヤッキー、トンズラーは、
「大切な人を守れなかったから」
そう言った。
ガリナは、夜なべをして、ドロンボー一味の衣装を縫い、それを託す。
ドロンボー一味が去った後、アルエットの家を、ヤッターマンロボが襲撃していた。
2人の居場所を言え!
そこに戻ってくるドロンボー一味。
「お前たちを守る!」
一緒に進むことを自分で決めるガリナ。
燃え盛る家から現れる正装のドロンボー一味。かっこいい。
「お前たちは本当の正義なんかじゃあない!」
「清く正しく美しく! ドロンボーがいるかぎり、この世にヤッターマンは栄えない!」
「闇をはらい、この世界に新たなる夜明けを!」
ボヤッキーのロボで窮地を脱出するドロンボー達。
(続く)。
まさかのみんなで行く展開に。特にすごい力があるわけでもないけれども、
仲間が増えて、進んでいくのですね。
衣装で登場するところはかっこいいですねぇ。
「お前たちは正義なんかじゃあない!」というところ、いいですねぇ。
まさにその通り! ヤッターマンは悪党だ! 気持ちがスカッとしました。
この後、どうなっていくのでしょうか。
